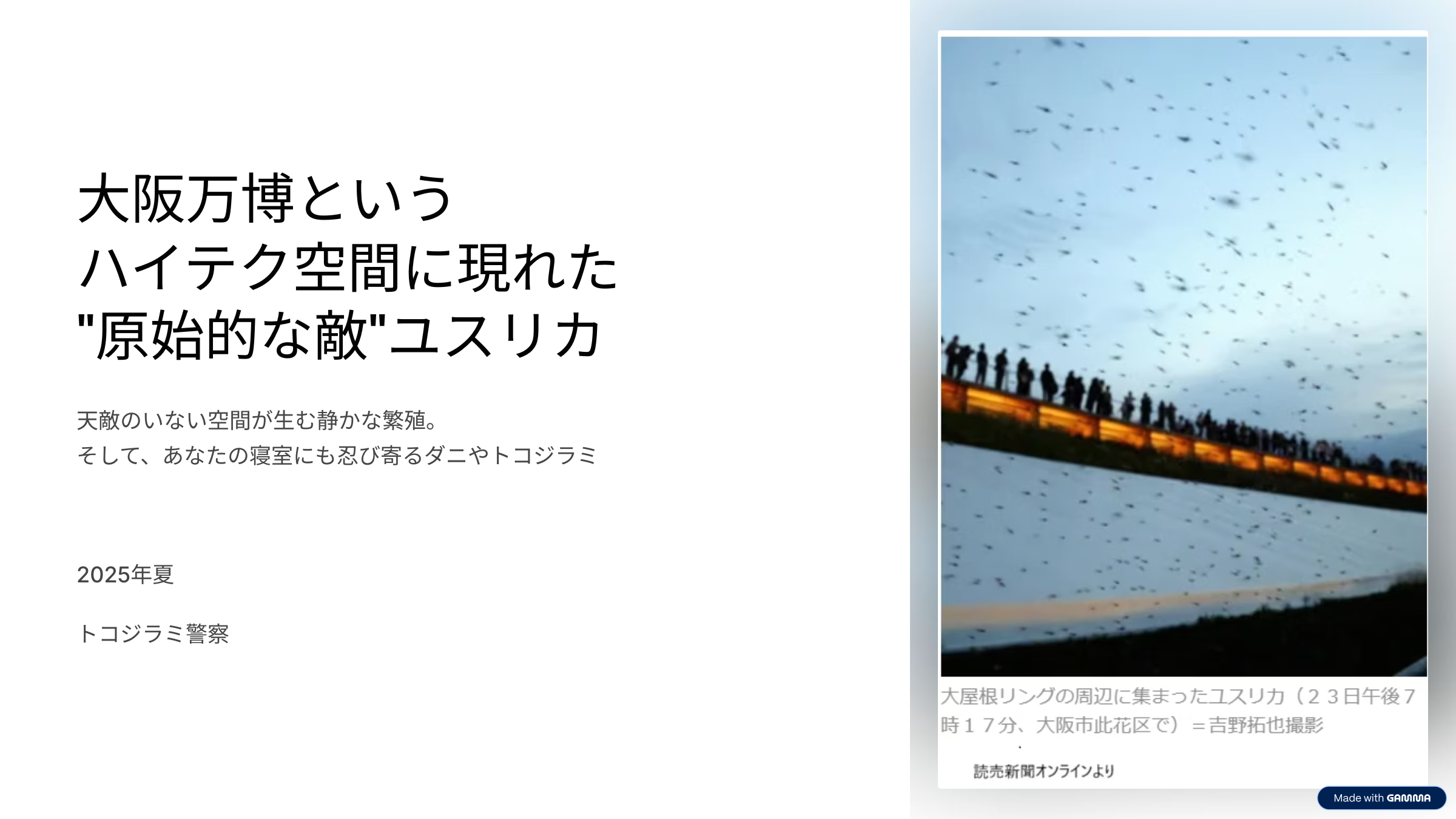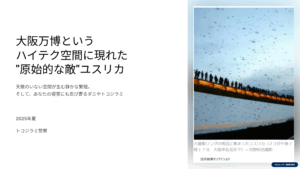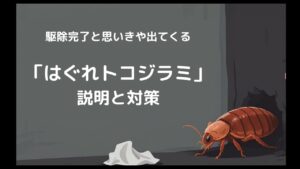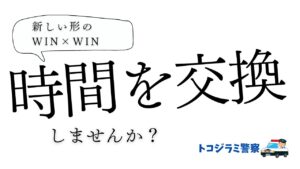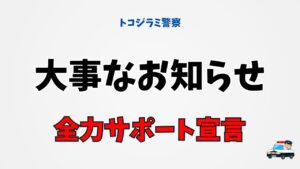万博に現れた“虫”が、なぜこれほど話題になったのか?
今、SNSで話題になっている「ユスリカ大量発生」。
その舞台は、最新テクノロジーの粋を集めた大阪・関西万博の会場です。
未来的な展示が並ぶ会場に突如現れた、原始的な敵――それがユスリカ。
刺すわけでも毒があるわけでもない。
けれど、群がり、まとわりつき、不快感を与える存在として、
多くの人の注目を集めました。
一部では「万博の失敗だ」と非難される声もありましたが、
実はこの現象は、私たちの生活とも無関係ではないのです。
虫が増えたのは“人間が作った環境”のせいだった?
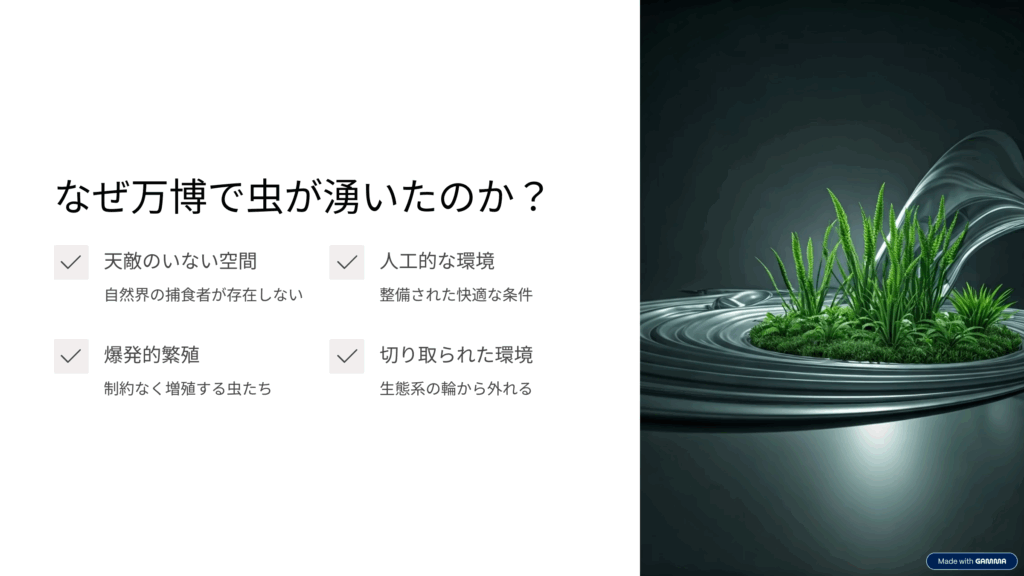
なぜユスリカがあれほど増えたのか。
それは、「天敵のいない空間」がそこにあったからです。
本来、自然界ではユスリカを食べる鳥やトンボ、小さな捕食者たちが存在します。
しかし、万博会場という切り取られた人工環境には、そういった天敵がいません。
その結果、安全で快適な空間に大量の虫が集まり、繁殖の場になったのです。
つまりこれは、「最新技術」と「生態系の不在」が矛盾した形で同居していた結果といえます。
実は、あなたの寝室も同じ構造をしている

「そんなの万博の話でしょ?」と思うかもしれません。
けれど、同じような環境が、実はあなたの寝室にもあるのです。
最近の住まいは高気密・高断熱。
エアコンや加湿器で年中快適。
布団、カーペット、ぬいぐるみ…布製品もたくさん。
そして何より、虫の天敵はいない。
この環境で静かに増えているのが、
ダニや**トコジラミ(ナンキンムシ)**といった存在です。
ダニとトコジラミ──“絶滅しない虫”があなたの生活に潜む
ダニはハウスダストの主成分になり、
アレルギーや喘息、皮膚炎の原因にもなります。
とくに寝具やカーペットに潜みやすく、外からは見えません。
最近話題なのがトコジラミ。
一度侵入すれば、家具の隙間や壁の裏に潜み、
夜になると出てきて人の血を吸うという生活スタイル。
近年では薬剤耐性を持つ個体も増えており、
市販の殺虫剤では太刀打ちできないケースも珍しくありません。
トコジラミは“建物内で完結するライフサイクル”を持ち、
外の天敵を必要としません。
まさに「人工環境に最適化された虫」なのです。
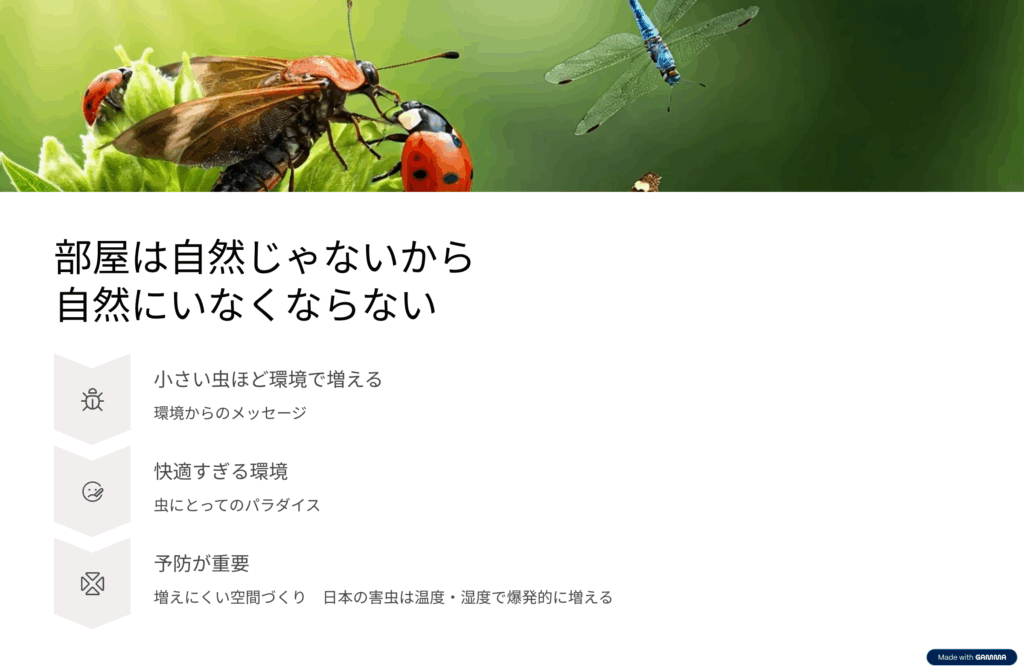
私たちが虫とどう向き合うか──駆除より“環境づくり”
虫は“敵”ではありません。
彼らは環境に敏感に反応する、いわば自然からのセンサーです。
ユスリカも、トコジラミも、増えるには理由があります。
それは**「ここなら安全」「ここは快適」**と判断された結果なのです。
AIがどれだけ進化しても、虫は滅びません。
虫の絶滅は、生態系の崩壊と同義です。
だからこそ大事なのは、“共存”ではなく“適切な距離感”。
虫が増えすぎない環境を、あらかじめ整えることです。
たとえば――
- ダニには防ダニシーツや布団乾燥で繁殖ブロック
- トコジラミにはベッドフレームの見直しや隙間対策
- 布製品を減らすだけでも、虫にとっての居場所は激減します

最後に:ユスリカが教えてくれた“虫のメッセージ”
万博に現れたユスリカは、決して“異常”ではありません。
それは現代の建築や都市環境が抱える構造的な問題を
私たちに突きつけた象徴です。
そして、同じ構造は寝室にも存在しています。
そこに増えているのは、見えないダニや、夜に忍び寄るトコジラミ。
静かな繁殖のサインを見逃さないこと。
そして“虫が生きられない環境”を人間が先に整えること。
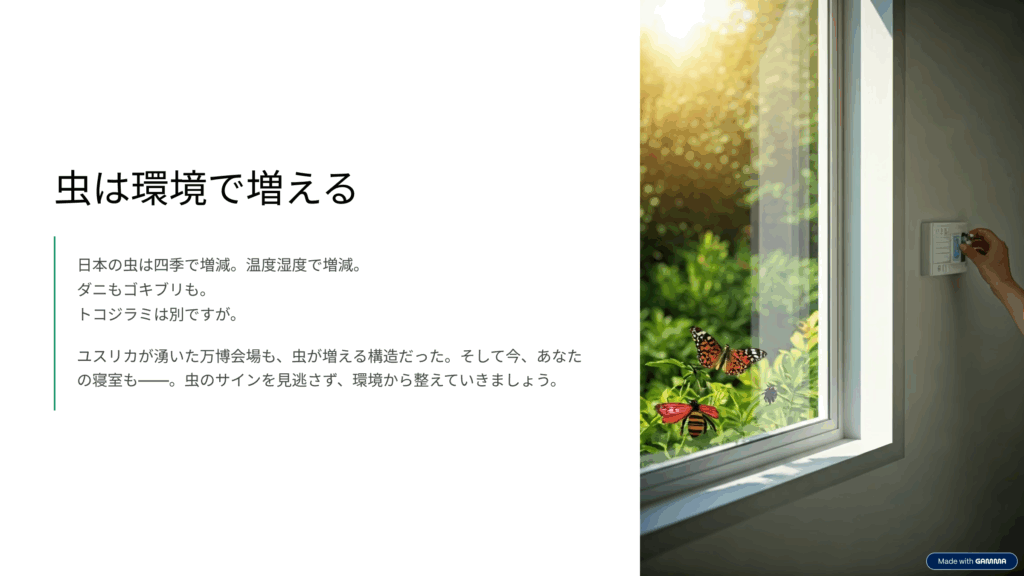
それが、快適な暮らしを守る最大の防御になります。
トコジラミ警察は365日ご相談にのってます。
お気軽にLINEからご連絡ください。